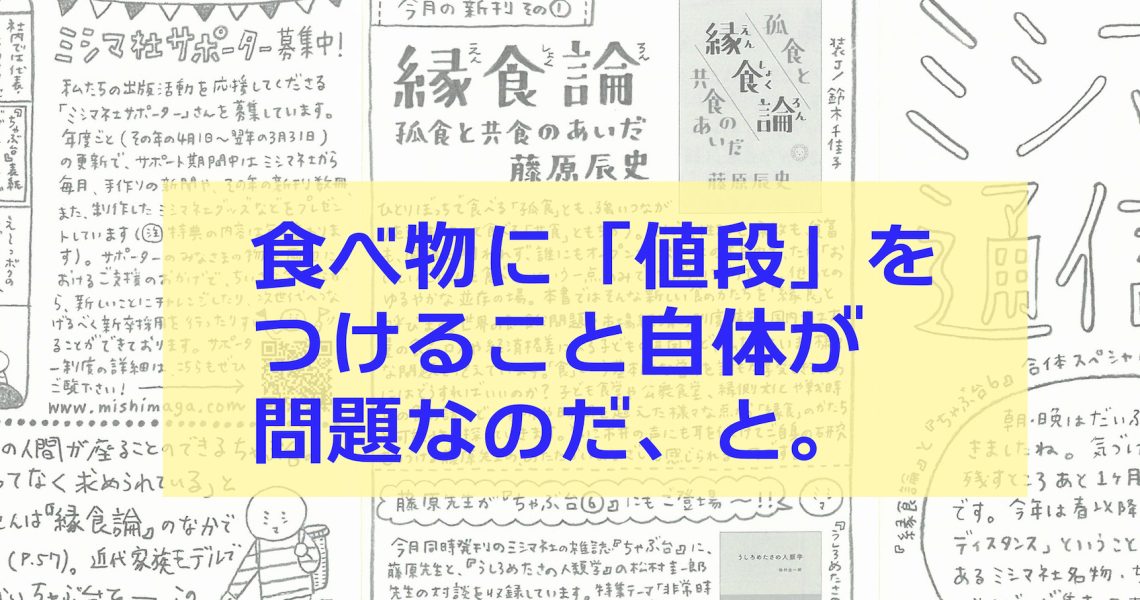『縁食論 孤食と共食のあいだ』〜食の商品化に無理がある〜
先日読んだ『縁食論 孤食と共食のあいだ』です。たまたまメルカリを調べていて安く提供されていたので入手。2020年11月に出版されていたのですが、もっと早く読んでおけばよかったなあと思いました。
ちなみに、「日本の古本屋」やアマゾンの古本では商品の状態を十分判断できないので「一か八か」の賭けみたいになってしまう面があり、そこは写真で判断しやすいメルカリが有利ですね。
フェイスブックとインスタの投稿の追記部分を以下に貼り付けます。
誰にでも無料または低価格で食が提供される公衆食堂には、語らいの場ができ、人々が交流する場ともなり、それは社会の土台を強くする役割があります。ドイツでもインドでもそして日本でも、古くからそうした場所はあったといいます。
格差が広がる日本でこども食堂が大事な役割を果たし、たちまちのうちに広がりました。その存在意義の説明は不要ですが、こども食堂だけにその仕事を押しつけるような今の社会の問題点も浮き彫りにしています。
藤原さんは、食という(水や空気や土地といったものもそうですが)生命の源となるものに「値段」をつけること自体に疑問を投げかけています。公衆食堂が無料で(または市場価格とは比較にならない低価格で)食を提供し、それが社会に広く求められていることは、食の脱商品化に向けた橋渡し的役割が公衆食堂にはあるのではないかと強調されています。
醤油や味噌の貸し借り、近所同士の「おたがいさま」といった関係性で成り立つ社会は、「市場経済」が全てではないことを示していると思いますが、実は価格をつけないという非市場経済こそが本来の人間社会の姿なのではないかと気付かされました。殺伐とした自己責任社会で、差別や分断が人々を苦しめており、今何とかなっている人々をも蝕んでいる中で、食という最も大事な生命活動にこそ人間らしさが生まれる根源があるのに、食べることすら出来なくなっているような現実を放置していて良いのかとの強い批判が根底にあります。そうだからこそ、人々の苦しみや人間らしさの発現への非常に温かい捉え方ができるのだと思いました。所々で涙したのはそれが理由だったのだと振り返っています。
人が生きていくためには衣食住が大事ですが、食というのは他の二つに比べてもより優先的な要素です。その食に在り付けない人がこの日本にも増えているし、世界では途上国などで1日1食も食べられない人が多数存在します。一方で毎日たくさんの食品ロスが生まれ、食べられる食品が無慈悲に廃棄されています。鮮度が悪くなれば商品としての価値がなくなるし、そうした商品を市場に残しておけば商品の過剰から全体の価格を下げてしまうため、直ちに市場から排除されなければならないのです。食品市場は、食品廃棄が前提に存立していることになります。
栄養を必要とする人が、【お金がない】というだけで、目の前にある食品を〜しかも、売れ残り廃棄が確実な運命にある食品があるというのに〜手にする事ができないのです。
今食べなければ命が尽きるかもしれないという人に対して「金払うのが当たり前だろ」という言葉しか返さない社会でいいのでしょうか。
「立派な自動車をもち、家があり、十分な栄養をとれている人が、千円足りなかったばっかりに今晩は和牛肉ステーキが食べられなかった。悔しい!!」というのとはまったく別次元の話です。
市場とは、人間労働の平等性を基礎に商品の価値を測る(貨幣で正確に表現する)ことができる社会機能です。その市場経済の最も発達した資本主義社会は、ある意味、誰にでも公平で平等な社会です。
しかし、それは、所得に格差がないという前提の場合に限っての話です。市場経済にも、商品にも何ら罪はありません。悪いのは、所得の格差を生み出すシステムです。どんなに市場が平等に価格をつけても、その価格では買えない人を資本主義社会が生み出し続ける以上、それは不平等な社会だということです。
藤原さんは同書の64ページで、次のようにいいます。
「食料の自給自足を完全にまたは一部だけ営む人が増えることで、食が脱商品化していく可能性もある」
「こうした社会は簡単にいえば、食費がかからない社会でもある。高級料理店は例外的にお金を払うにしても、農家も漁家もパン屋も食堂もみなが地域の税金のようなものによって運営または補助されていて、食べ物は基本的人権の当然の行為として自由に食べることができる。数百年も昔の人々は、水や土に値段が付けられるなんて考えもしなかっただろう。いまは、ミネラルウォーターにも、プランターに入れる土にも値段がある。人間が空気を自由に吸うことや、日光を自由に浴びることは現段階では許されているが、空気や日光に、一時間五百円、いまならなんと半額、などのような値段をつけられる世界など、およそ考えたくない。(略)だから、空気や日光のように自由に食べものを得られる社会を想像したって、罰当たりではないだろう。」
また、同書73ページで、「食べものの商品への馴染みにくさの根源はどこにあるか」との問いを立てたうえで、次のように回答しています。
「第一に、目の前のおにぎりを食べないと明日の生命が危うい人間にとっての1個のおにぎりの価値と、目の前のおにぎりを食べなくても明日の食が確保されている人間にとっての1個のおにぎりの価値の間の乖離は、測ることができないほど隔絶しているにもかかわらず、市場は価値が同じとみなすからである。携帯電話やテレビとは比べ物にならないおにぎりという存在の重さを測り損なうからである。」
「第二に、食べ物はかつての生き物であり、死んだあとも刻々と変化していく。それに固定した値段を付けることは、じつは論理的ではない。食べものの腐敗性は、タイムセールだけではカバーできず、ついには、廃棄し焼却することで(堆肥化、飼料化したものをのぞき)、食べものを商品世界から追放して解決が試みられているにすぎない。」
市場という絶対存在の呪縛から抜け出した視点には、今日の社会を本質的に批判する力があります。

では、「基本的人権の当然の行為」(p64)ができない、つまり食べる権利が剥奪された人々を生み出している深刻な現状を、どうやって解決していくのか?
ありきたりの言葉で言えば社会保障、社会の救済策の強化なのだと思いますが、藤原さんはさまざまな支援団体や個人がとりくむ「子ども食堂」や「公衆食堂」に光をあてます。そこでは、所得にかかわらず食事が誰にでも提供されることの意義を強調すると同時に、気兼ねなく誰でもいつでも立ち寄って交流し、壊された人間性を回復する場、社会で起きているさまざまな問題(DVや差別、格差拡大・・・)を見つめそれを打開する方策を考える場、政治を語り合い変革していく知恵を集める場にもなっていくというところに注目をしているのです。お金のない人もある人も同じ人間として等しく扱われ人々をエンパワメントしていく場、社会を変えていく力を生み出す場にもなりうる食堂が、いろいろな形態で全国各地に広がっていることが大事だというわけです。
藤原さんは、食べものの脱商品化というのはそう簡単なことではないが、脱商品化した領域を徐々に広げていくことが大事だろうと提起します。(71ページ)
「将来の食べものの脱商品化に向けて徐々に人々の感覚と世の中の雰囲気を慣らしていくウォーミングアップの場所の設計をしてみる。『円』ではなく『縁』で食を回す実験的空間を作ってみる。初めは食べものに値段がついていてもよいかもしれない。それを徐々に安くし、つぎはカンパ制にし、値段を無意味化していく。この空間に来さえすれば、食事はほかよりも安く食べられる。そして、いつかは、インドのシク教徒の寺院のように、宗派、性別、思想、門別に関係なく、誰でも無償でカレーを食べることのできる公衆食堂が世界各地に登場する社会を構想すると、肩から大きな負荷をふっと下ろす感覚にならないだろうか。」

「食べものはお金を払って手に入れるもの」という今の私たちの常識は、ホモサピエンスの人類史数十万年の中のわずか数百年のことです。空気や水と同様、食べ物も本来みんなのものであり、かつ自分のものである財産であって、無償で手に入れられるはずのものではないかと。この視点は、資本主義を乗り越えた未来社会を展望する際に大事な観点だろうと思います。